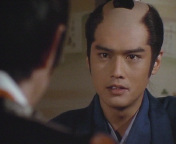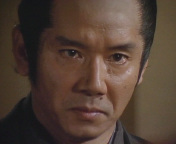| 白虎隊TOP ⇒ 前篇TOP ⇒ 前篇 其の4 ② |
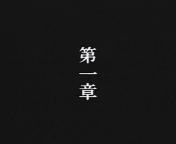



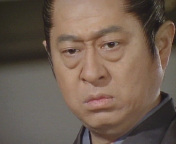

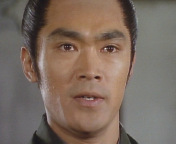




 「キク」
「キク」


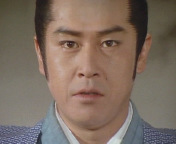
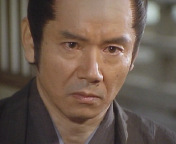

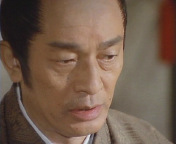



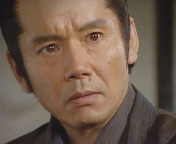


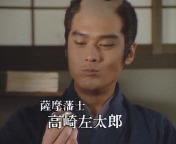 「高崎左太郎(たかさき さたろう)」
「高崎左太郎(たかさき さたろう)」





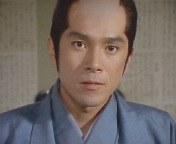
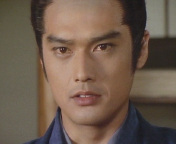

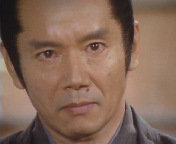
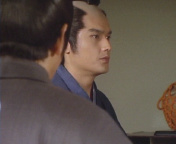


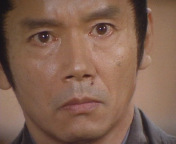
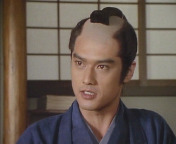
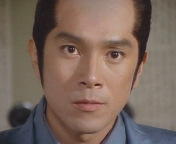




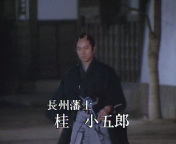 「桂小五郎(かつら こごろう)」
「桂小五郎(かつら こごろう)」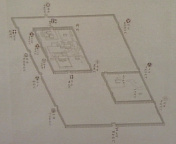
 |
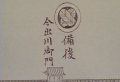 |
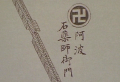 |
| 乾御門:薩摩 | 今出川御門:備後 | 石薬師御門:阿波 |
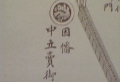 |
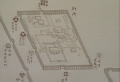 |
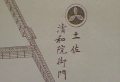 |
| 中立売御門:因幡 | 朔平門:奥平 皇后門:京都所司代 清所門:京都所司代 宣秋門:会津 建礼門:薩摩 建春門:米沢 |
清和院御門:土佐 |
 |
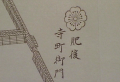 |
|
| 蛤御門:水戸 | 寺町御門:肥後 | |
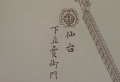 |
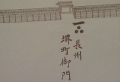 |
|
| 下立売御門:仙台 | 堺町御門:長州 |